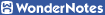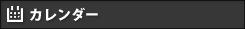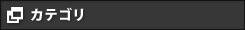2011.05.31 UP
『アジャストメント』
『アジャストメント』@新宿ピカデリー
サスペンスなので、まずは導入部分の筋を。
>主人公・デヴィッドは、アメリカ合衆国議会の上院議員候補。彼はある日、ダンサーであるエリースと運命的な出会いを果たす。2人が結ばれるのは時間の問題だったが、謎の集団にデヴィッドはさらわれてしまう・・・
とまあ、サスペンスなのでここまでしか書けません。
フィリップ・K・ディックの原作『調整班』は未読です。短編を長編映画に引き延ばしたらしいですね。
・・・サスペンスはこれ以上書けないのがつらい。
・・・ヒロインのエミリー・ブラントが光っています。
・・・マット・デイモンはいつものごとく頑張っています。
・・・「調整」というアレの視点も気持ちいい。
・・・106分も適尺ですね。
タイトルにもなっている、「調整」シーンがあるんですが、このシーンは最高です。世界が歪む瞬間に出会えます。
ああ、書けないのがつらい。こういった作品はみんなで観に行ってから30分喫茶店で語る、ような展開が望ましいですね。いちいち書くことも野暮ですし。とはいえ、良作です。最近で言うと、『アンノーン』とこの『アジャストメント』を両方観ると、2011年度版ヒッチコック風味が堪能できます。
最後に1つ。国民的漫画のあのガジェットそのままの設定、疾走感が半端ないです。
2011.05.26 UP
『ブラック・スワン』
『ブラック・スワン』@新宿バルト9
ダーレン・アロノフスキーの新作、楽しみにしていました。
監督作としては最新作ですが、フィルモグラフィ的には製作総指揮の『ザ・ファイター』が最新になるんでしょうか。それにしても、『レスラー』と『ザ・ファイター』の間にこの『ブラック・スワン』がくるとは慌ただしいラインナップですね。
プロレスラー → バレリーナ → ボクサー、とフィジカルな映画が3本続いたことになります。この点は重要でしょう。アロノフスキー初期の「思考映画」とも呼ぶべき『π』や『レクイエム・フォー・ドリーム』とのルックスの違いに驚きますが、本質的には「極限の人間はどんな行動をするか」を徹底して描き続けた作家だと思います。
さて、『ブラック・スワン』ですが、『八日目の蝉』の井上真央よろしく、ナタリー・ポートマンの実人生と物語のリンクにより、画の凄みが増すという、観客にとってはプラスしかないキャスティング手法は最高ですね。
「お前の潔白なホワイト・スワンは完璧だが、官能的なブラック・スワンはまったくダメだ!!」という劇中の指摘は、「お前は清純派女優としては完璧だが、型にはまりすぎでもう1歩足りないんだよなぁ」という現実のナタリー・ポートマンに呼応します。
と同時にこれはアロノフスキー自信にも跳ね返ってくる言葉でもあります。「お前はロジック映画としては完璧だが、芸術という意味でもう1歩足りないんだよなぁ」と。
それに対する立派な答えを、ラストカットできっちり示していると感服しました。もし、完璧な芸術というものがこの世に存在するとしたら、こんな形でしかあり得ないのじゃないか、という前近代的な提示は、フィジカルな作品を3作続けた男の宣言であります。その力強い宣言を豪腕で自分でねじ伏せる。天晴れです。
タマフル情報ですが、クラブのシーンではサブリミナル的に様々なカットが挟まれているみたいですね。ストロボの最中、ナタリー・ポートマン以外の人が全員同じ顔になっていたり・・・などなど。あのシーンも素晴らしかった。クラブシーンでいうと、最近だと『ソーシャル・ネットワーク』でもクラブシーンがありましたが、あそこではザッカーバーグがショーン・パーカーとクラブの中2階みたいなところで密談をするというものでした。それに比べて『ブラック・スワン』ではフロアで思いっきりダンスします。しかもストロボで。フィジカルな映画というのは、そういった1つ1つのシーンの積み重ねなんだなぁ、と再確認しました。もちろん、『ソーシャル・ネットワーク』のそのシーンもIT的に言えば正解なんだと思いますが。これ以外にもクラブシーンがある映画は多いです。時間があったら比較・分析してみたいなぁ。
そのシーンを確認するためだけでも、これはもう1回観に行かなくては、ですね。
2011.05.21 UP
『人生万歳』
『人生万歳』@DVD
基本的にこのブログでは劇場で観た映画しか紹介していないのですが、今回は例外です。
ウディ・アレンの監督としての長編40作品目(!!!!!!!)です。指摘するのも野暮ですが、この作品数はやはり驚異的ですね。現在、75歳の老映像作家としても、世界に例が少ないのではないのでしょうか。もちろん、高齢で映画を撮り続ける作家はたくさんいますが、1年に1作というペースを頑なに守り続けて40年超え。・・・まさに「お疲れ様です!!!!!!!!!!!!!!!!!!」。僕らが普段使っている「お疲れ様」に申し訳ない気持ちでいっぱいです。
とはいえ、褒められるべきはその量ではなく、質です。中期の作品はもちろんのこと、2000年代に入ってからの『おいしい生活』や『さよなら、さよならハリウッド』や『メリンダとメリンダ』など地味ながらも深い揺さぶりをもたらす佳作を連発しています。
そこで、日本公開最新作『人生万歳』です。
654ページの大著『ウディ・アレンの映画術』の中で本人自らは「僕の映画に特徴がもしあるとしたら、それは登場人物が観客に直接語りかけることかな」と認識しているように、『人生万歳』は『アニー・ホール』から続く、純情派メタフィクションものです。
「この作品は現代版『アニー・ホール』である」と指摘して何の意味があるでしょうか? たしかにそうなんです。元となった脚本が書かれた時期も近いことも関係あるのでしょう。でも、2作品を比較するのは映画の評価ではなく、時代の評価になってしまう気がします。「この時代の空気を非常に敏感に察知して・・・」うんぬんになります。そうではなく、2作品の共通性にこそ普遍性があるはずです。
とはいえ、1つだけ指摘しておきたいのは『人生万歳』での「観客」の扱い方です。主人公はただ我々に直接語りかけてくるだけではありません。「自分が映画だ」と言い張るのです。「あなたたちは、僕の映画を観ている客である」とまで言います。なぜ、我々はそこまで物語から突き放されなければならないのでしょうか。「こんなつまらない作品を観るな」とまで直接言われながら。