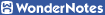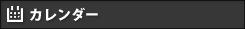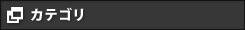2011.06.15 UP
『さや侍』
『さや侍』@渋谷シネパレス
松本人志監督の3作品目は、父親と娘の物語です。
いくつか箇条書きで問題提起だけ。
●素人の王様、野見さんの狂気がどこまでスクリーンに写っているのか?
●「父親と娘の関係性」という、ド直球すぎる物語に2011年に公開すべき“ひねり”が加えられているのか?
●単調になりがちな構造「30日の業」は変化に富んだ演出がなされているか?
●「さや」しか持たない侍は、なぜ刀を手にしないのか?
観る前でも、観終わった後でも、これらの疑問は有効でしょう。
「『映画』のための映画」とでもいいましょうか。それがきちんと脱構築されたものであれば刺激的で、猛烈な魅力を放つことでしょう。「壊す」ためには、その「壊す」ものを直視しなくてはなりません。自分で作ったつたない粘土を壊すことが前衛的なわけはありません。むしろ、そのつたない粘土の素晴らしさを語り続けること、それが真の前衛だと信じるしかないのです。
2011.06.12 UP
『悪魔を見た』
『悪魔を見た』@シネマート六本木
公開からかなり遅れたんですが、“韓国映画ならロングラン”ことシネマート六本木に行ってきました。
お客は僕を含めて、3名という渋めの上演で、プライベートルーム的にリラックスして鑑賞しました。が、内容は全くリラックスしないというアクロバティックな時間でした。
イ・ビョンホン目当てのおばさまがこの映画を観て「こんなつもりじゃなかった」と涙目で映画館を後にする、そんな噂を聞くほどです。それほどまでにショッキングな内容である、と事前情報で耳に挟んでいました。
結果、どうだったか。たしかに暴力描写は凄まじいものがあります。
そして、テーマはド直球。
「復讐はどこまで復讐できるのか」
復讐は連鎖していくものかもしれない。しかし、どこまで復讐を突き詰めることができるのか。どこまで復讐すれば、スッキリするのか。そこを徹底して描いていきます・・・。
もちろん、結論は観客がそれぞれ持ち帰るべきものです。
僕の結論はこうです。
「どこまで復讐しても絶対にスッキリしないから、別にしなくてもよくね?」
という身も蓋もない結論でした。そこを含めて「当事者にしか分からない苦しみがある」というメッセージは消されます。なぜなら、当事者などどこにもいないからです。たとえ、最愛な人を失ったとしても。
2011.06.01 UP
『マイ・バック・ページ』
『マイ・バック・ページ』@新宿ピカデリー
川本三郎の原作『マイ・バック・ページ』(平凡社)をしっかり読んでから劇場へ。そしてユリイカの山下敦弘特集も熟読。(巻頭の「山下+向井」対談は読み応え抜群)ハードルは上がりまくっていました。
そのハードルを平気で超えてきました、この映画は。
ポイントは、原作の川本本人の甘ったるさを映画ではどう表現しているのか? そして、フィクションとして何を足して、何を引いたか? こんなことをつらつら思いながら劇場に入りました。
甘ったるさは、そのまま。というより妻夫木聡の童顔により、甘ったるさが倍増、といった感じです。
足された部分はたくさんありますが、一番大きなのは記者時代に潜入取材した部分のディティールでしょう。(これが大きく物語に影響を与えるのですが、ネタばらしになるため省略)
引いた部分は「腕章」です。殺人事件の証拠となる腕章。原作では腕章についてたっぷり筆が費やされます。映画ではほとんど話題にもなりません。あとはジャーナリスト魂。これが引かれています。ジャーナリスト精神の葛藤は映画ではほとんど描かれません。
ニンマリしたのは、主人公が川島雄三『洲崎パラダイス 赤信号』を観ているシーン。その冒頭シーン。「あんたもっとしっかりしなさいよ」と新珠三千代が三橋達也に説教するシーン。これはそのまま『マイ・バック・ページ』主人公にも跳ね返ってくる言葉です。センチメンタルな男に対しての。と、劇中で登場する映画と比べてみても・・・ただの悪趣味になりそうなのでやめます。
「本物」を目指した男2人の悲劇、そうまとめていいんでしょうか? もしくは「本物」になれなかった男2人。そもそも「本物」とは何なんでしょうか? この2人は自ら「本物」になろうともがきます。でも、「本物」とは自分からなりにいくものなのでしょうか? 「本物」は「コレができたら本物だ」と考えない人種のことなのでしょうか? 少なくとも最低条件ではあるでしょう。自称・天才がいかがわしいのと同様、自称・本物だって怪しいモノです。と分かっていても「本物」になりたい。そんな時代だったのでしょうか? 本当にそうでしょうか? <「本物」は「コレができたら本物だ」と考えない人種>だから敢えてそんなことを言わない、という本物だっていそうなものです。つまり、「本物かどうか」なんて誰にも分からないのです。誰にも分からないモノになりたい、という動機は無限に続きます。終わりは「死」だけです。死ぬことだけは「本物」だからです。本作で主人公は「死んだ」のでしょうか?(さっきから疑問ばっかりですが・・・)新聞記者としては「死んだ」はずです。解雇されるのですから。本物の新聞記者にはなれなかった・・・。それなのに生きている・・・。そのリアリティーだけが本物を生み出すのでしょう。つまり、「本物になれなかったことで本物になる」という自己矛盾。それすらもノスタルジーで甘ったるいと笑われる存在なのでしょうか? 違います。と私は断言します。