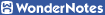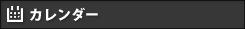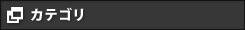2011.07.22 UP
『コクリコ坂から』
『コクリコ坂から』@TOHOシネマズ渋谷
劇場は公開初日。お年寄りから高校生男子3人組、子供連れからアニメーションファンまで。様々な人々で溢れていました。
そんな光景はジブリ作品でしか見られないので、席に座っただけでちょっと幸せな気持ちになります。(ハリウッド大作には家族はほとんどいません)
つまり、日本人なら誰でも気軽に「観に行こうか」と思えるジャンルとして確立しているジブリ作品。宮崎駿の狂気が大衆を呼び寄せている、という事実に歪んだ日本社会を連想せざるを得なかった2000年代。
しかし、現在は2011年。宮崎駿は自分で企画し脚本を書き、息子の宮崎吾郎に監督を任せます。(本意ではないかもしれませんが)
キャッチコピーは「上を向いて歩こう」。(同タイトルの歌が劇中で2回流れます)
物語は少女と青年の恋愛を軸にして、1963年の横浜を舞台に進んでいきます。東京オリンピック前年の設定が、高度経済成長真っ直中の横浜を活気づけています。(この時代変更が、原作漫画からの大きな変更点の1つです)
プロダクションノートによると、宮崎駿の脚本にあった台詞の間にある「・・・」、つまり「タメ」を監督は削ってしまい、テンポのある会話に変更したそうです。そのスピードは成功していると思います。少女と青年の会話は、テンポを上げたことによって、現代の若者にも見える形になっています。これが「タメ」の連続だったら・・・重苦しい映画になっていたでしょう。これは腕力のある演出です。「タメ」で何かを語っているような気にする逃げの演出よりどれだけマシでしょうか。
印象的なシーンは映画冒頭です。
主人公・海が自宅で料理をしているシーン。
テンポよく、朝食を準備する海。料理家庭を丁寧に見せていきながら、その家庭環境の描写にもなっており、さらにメニューによって時代背景を知らせてくれる。そこにはヴォーカル入りの「朝食」という曲がかかっており、ミュージカル的な要素も入っています。
そして、家族全員で「いただきます」との発声。
「食」から始まる映画なわけです。
もう1つも「食」に関するシーン。
主人公・海がコロッケを青年にもらうシーン。(このシーンは脚本作りの際に、宮崎駿が実演して振り付けをしたシーンらしいです)
このコロッケのシーンが生み出されるのも、海がカレーを作ろうと思うが、お肉が冷蔵庫になく、買い出しにでかけるというエピソードからです。
「食」の映画といっても過言ではありません。
このように食事シーンが素晴らしい演出をされている場合、その映画は大成功と言い切ってしまいます。(ジョニー・トー監督と同じ。フード理論w)
付け加えるなら、アニメーションはどうしても物語の重要シーンなどのメインの動きに力を入れがちです。食事シーンなどはどうしても手を抜いてしまい、美味しそうな食事シーンのあるアニメは少ないです。思い出してください。例えば、サザエさんの食事シーンを。あそこのご飯を「食べてみたいな−」と思ったことのある人はほとんどいないはずです。
もちろん、食事以外にもたくさん素晴らしいカットはあるんですが、それもすべて食事のディティールあってこそ、と言い切りたい誘惑に駆られます。
とにかく「コクリコ坂」のご飯に注目です。
2011.07.09 UP
『奇跡』
『奇跡』@新宿バルト9
2011年3月に全線開通した九州新幹線をモチーフにした映画です。
とはいっても九州新幹線は、ほとんど登場しません。
メインとなるのは、まえだまえだの2人の奔放さと成長です。
>せりふが決められていない状況の中で周囲の友人たちに突然質問されることによって、普段考えていることよりも、一歩深く踏み込んだところにある感情を引き出すことができる、というのが是枝監督の持論
この手法は今作でも有効です。
しかしこの手法、僕は映画としては決定的に欠けてしまうものがあると思います。
「普段考えていることよりも、一歩深く踏み込んだところにある感情」というものこそ、作劇によって出現させるのが映画じゃないですか。それがフィクションの強度でしょう。
それらを子どものアドリブに託す。ああ、なんて野暮な手法なんでしょうか。映画のリアルを、即興のリアルに置き換えるなんて。
一見すると、それらのシーンはリアルに感じられます。でも、本当のリアルに違和感があったとしたら? 例えば、それまでは役者が演技を続けていて、いきなり「本当のリアル」になったとしたら? それ自体が違和感になりはしないでしょうか。それはフィクションとノンフィクションを行き来する差異ではなく、ただの違和です。
しかも、その違和はフィルムをぎくしゃくさせるだけなのですから。
【重要】くるりのエンディング曲『奇跡』は、恐ろしく素晴らしいです。
2011.07.04 UP
『東京公園』
『東京公園』@新宿バルト9
>「東京バンドワゴン」でブレイクした小路幸也の同名小説が原作。公園で家族写真を撮り続ける光司のもとへ、「彼女を尾行して写真を撮ってほしい」という依頼が舞い込んだことで、ゆるやかな距離でつながっていた女性たちとのあいまいな関係が微妙に変化していく……という物語。
青山真司監督、4年ぶりの新作です。
監督本人が今回のキャストについて「爽やかさを基準に選ばせていただきました」とコメントしている通り、主人公の三浦春馬、爽やかすぎます。
三浦春馬を劇場でしっかり観るのは初めてで、舐めていました。「どうせ、ただのテレビ俳優だろう」という偏見から入っているので、印象は最悪でした。この映画を見終わった後、やはり偏見は所詮、偏見であるという当たり前すぎる結論に。
三浦春馬は佇まいが良いですね。
物語は3人の女性に挟まれる男子大学生の揺れ動きをメインに、丹念にその過程を追っていきます。
・(死亡した)親友の元彼女
・血のつながっていない義理の姉
・母そっくりな人妻
この3人の中心に、主人公は佇んでいます。佇みながらカメラを観客に向けます。(つまり、映画のキャメラにカメラを向けます)
そのカメラが我々に向くとき、我々はそのカメラのアップを観ることになります。映画の撮影キャメラと、主人公のカメラ・・・その間にある空間に我々は放り出されたような、そんな「どこにもいないような」佇まいになります、自分が。その乱反射の背景には公園があります。公園が佇んでいます。
そんな公園を体感したくて、映画終わりで近所の公園に行きました。日曜日だったので、子どもがたくさん遊んでいました。
その子どもたちや家族を見て「これ全員エキストラだったら面白いな」と思ったんですが、エキストラであれ、現実の人間であれ、どっちでも同じだなぁ、と思いながら、自分の目から見える画角をじっと見つめていました。
東京の公園には色々な発見があります。