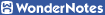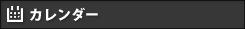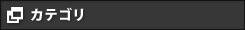2011.05.24 UP
『八日目の蝉』
『八日目の蝉』@渋谷東急
『八日目の蝉』という単語は劇中で2回登場します。
1回目は井上真央演じる秋山恵理菜のセリフです。
「蝉は七日しか生きることができないけど、もし八日目まで生きる蝉がいたら悲しいと思う。なぜなら(蝉の)知人がすべて死んでしまい一人ぼっちだから(要旨)」
2回目は小池栄子演じる安藤千草のセリフです。
「こないだ八日目の蝉の話、したでしょう。もしかしたら、八日目の蝉って悲しいんじゃなくて、みんなが見ていない素晴らしいモノを見ることができて幸せなのかもしれない(要旨)」
前者は「生きることは苦しいことだ」と考えます。後者は「生きることは苦しいことばかりではない。素晴らしい体験ができるんだ」と強く人生を肯定します。
この通俗性をどう考えればいいのでしょうか。通俗性と普遍性は常に隣り合わせです。それ故にこのラインは「この作品は通俗で価値がない」と断言されたり、はたまた「普遍的で価値ある作品だ」と評価が真逆になる危うい橋でもあります。
正直な気持ちを言うと、通俗的であろうと普遍的であろうと、どっちでもいいのです。
ただ観ているだけですから。
最後に井上真央について。「幼少期を子役として過ごした時間」=「誘拐された幼少期」という実生活と物語をリンクさせるキャスティングは『ブラック・スワン』のナタリー・ポートマンと同じ構造です。単純に女優のモチベーションが違うというのは観客にとって、その前知識のありなしに関わらず、僕は大賛成です。
2011.05.21 UP
『人生万歳』
『人生万歳』@DVD
基本的にこのブログでは劇場で観た映画しか紹介していないのですが、今回は例外です。
ウディ・アレンの監督としての長編40作品目(!!!!!!!)です。指摘するのも野暮ですが、この作品数はやはり驚異的ですね。現在、75歳の老映像作家としても、世界に例が少ないのではないのでしょうか。もちろん、高齢で映画を撮り続ける作家はたくさんいますが、1年に1作というペースを頑なに守り続けて40年超え。・・・まさに「お疲れ様です!!!!!!!!!!!!!!!!!!」。僕らが普段使っている「お疲れ様」に申し訳ない気持ちでいっぱいです。
とはいえ、褒められるべきはその量ではなく、質です。中期の作品はもちろんのこと、2000年代に入ってからの『おいしい生活』や『さよなら、さよならハリウッド』や『メリンダとメリンダ』など地味ながらも深い揺さぶりをもたらす佳作を連発しています。
そこで、日本公開最新作『人生万歳』です。
654ページの大著『ウディ・アレンの映画術』の中で本人自らは「僕の映画に特徴がもしあるとしたら、それは登場人物が観客に直接語りかけることかな」と認識しているように、『人生万歳』は『アニー・ホール』から続く、純情派メタフィクションものです。
「この作品は現代版『アニー・ホール』である」と指摘して何の意味があるでしょうか? たしかにそうなんです。元となった脚本が書かれた時期も近いことも関係あるのでしょう。でも、2作品を比較するのは映画の評価ではなく、時代の評価になってしまう気がします。「この時代の空気を非常に敏感に察知して・・・」うんぬんになります。そうではなく、2作品の共通性にこそ普遍性があるはずです。
とはいえ、1つだけ指摘しておきたいのは『人生万歳』での「観客」の扱い方です。主人公はただ我々に直接語りかけてくるだけではありません。「自分が映画だ」と言い張るのです。「あなたたちは、僕の映画を観ている客である」とまで言います。なぜ、我々はそこまで物語から突き放されなければならないのでしょうか。「こんなつまらない作品を観るな」とまで直接言われながら。
2011.05.17 UP
『アンノウン』
『アンノウン』@新宿ピカデリー
大前提から話をすれば、リーアム・ニーソンが体を動かしている段階でにんまりしてしまいます。彼を好きになったのは『96時間』からなので最近です。『特攻野郎Aチーム』でも味を出していました。(調べてみると次回作は、『ハングオーバー2』じゃありませんか!! これは楽しみすぎますね)
というわけで、前評判が良い・悪い以前の問題で「評判がない」という最高の状態で劇場に向かえるのも、このあたりのゆるーい映画の特徴の1つですね。なにせ「ハードルがない」状態なので、100%自然体でレーンを走ることができるわけです。まさに理想の“着席”です。
<ベルリンを舞台に繰り広げられるアクション・スリラー>とのことなんですが、この類の作品には絶対のツッコミとして「なんで主人公はそんなにアクションできるんだよ!」というものがありますよね。そのツッコミがクリアになる設定に痺れました。脚本が練られている、というわけではなく(それももちろんあるんですが)、こういった通俗的なアクション・スリラーもそれなりに年月がたてば洗練されていくんだなぁ、という含蓄すら感じます。
「洗練された通俗さ」というのは駄作より断然気持ちいいです。本当はそんな作品を作るのは難しいはずなのに、映画文化が進化するとそういった作品が立て続けに出る時代が現れます。まさに、2010年代はそんな「洗練された通俗さ」を持つ作品が多い希有な時代になる気がします。進化と進化の間にある豊穣な時代とも呼ぶべきでしょうか。そうした作品に「中身がない」とか「深さがない」とか「メッセージ性が薄い」などと野暮につぶやいてみたところで、何も始まりません。だ、か、ら、こういった作品を僕は強く応援します。